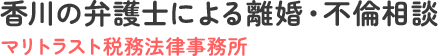親権・監護権・面会交流
離婚する際、未成年の子がいる場合は、親権や監護権、面会交流について取り決める必要があります。当事務所では、お子様の利益を第一に考え、解決に向けたサポートを提供します。
親権
親権とは、子どもの成長を助け、自立を促すために、子どもを養育し、財産を管理する権利と義務のことです。未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、夫婦のどちらか一方を親権者と定める必要があります。離婚後に親権者を変更することは非常に難しいため、離婚時に慎重に検討することが重要です。
親権者を決める判断基準
裁判所は、親権者を決定する際、以下の要素を総合的に考慮して判断します。
- 監護の継続性:現在子どもを養育している状況が継続されることが、子どもの生活環境の急激な変化を避ける観点から重要視されます。
- 子どもの意思:子どもが15歳以上の場合、子どもの意見を尊重することが原則とされています。
- 子どもに対する愛情:子どもへの深い愛情があるか、また、その表現があるかどうかが考慮されます。
- 経済的な安定性:親の経済状況が考慮されますが、経済力だけが唯一の判断基準ではありません。
- 心身の健康状態:親の心身の健康状態が子育てに適しているかが考慮されます。
- 別居中の監護状況:別居後の子育ての実績が考慮されます。
監護権
監護権とは、子どもを日常的に養育・世話をする権利と義務のことです。親権と監護権を分け、親権者ではない方が監護権者になることも可能です。ただし、監護権を分けることは稀であり、通常は親権者が監護権者となります。
面会交流
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らすことになった親と子が、定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることです。親権者ではない親と子どもが交流する権利は、子どもの健全な成長のために大切なものと考えられています。
面会交流の取り決め事項
面会交流の取り決めには、以下の内容を含めることが一般的です。
- 面会頻度:月に何回、何時間会うか。
- 面会方法:宿泊の有無、場所など。
- 連絡方法:電話やメールなどの頻度や方法。
- 費用の負担:面会にかかる交通費などの負担方法。
よくあるご質問
Q1:親権は母親が有利と聞きましたが本当ですか?
A:以前は母親が親権者となるケースが多い傾向がありましたが、近年では、母親か父親かという性別だけで判断されることはありません。裁判所は、お子様の養育環境やこれまでの監護状況などを総合的に判断して親権者を決定します。
Q2:親権と監護権は、分けて決めることができますか?
A:はい、親権と監護権は分けて定めることができます。しかし、監護権を分けることは非常に稀なケースです。通常は、親権者が監護権も有します。
Q3:親権を失った親は、子どもに会えなくなりますか?
A:親権を失ったとしても、親と子どもの関係がなくなるわけではありません。親権者ではない親と子どもが会う「面会交流」は、子どもの健全な成長のために重要なものと考えられています。親権者との話し合いで面会交流の取り決めができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、面会交流のルールを決めることも可能です。
当事務所の5つの特徴
当事務所は、宇多津・坂出・丸亀・善通寺・観音寺等の香川県全域の皆様の法律相談に対応しています。
- 丁寧で分かりやすい説明 お客様のお悩みに真摯に向き合い、専門用語を避け、分かりやすく丁寧な説明を心がけています 。疑問があれば、お気軽にご質問ください。
- 初回相談時に費用見積もりを提示 安心してご依頼いただけるよう、初回相談時に費用の見積もりを提示いたします。
- 休日の相談にも対応 事前予約制で、休日のご相談にも対応しています。まずはお問い合わせください。
- 当日相談も可能 空きがある場合、当日のご相談も可能です。
- 電話相談も可能 「法律事務所に行くのはハードルが高い…」という方も、まずはお電話でご相談ください。法的に解決可能な事案かどうかを判断いたします。